よみがな あり|なし
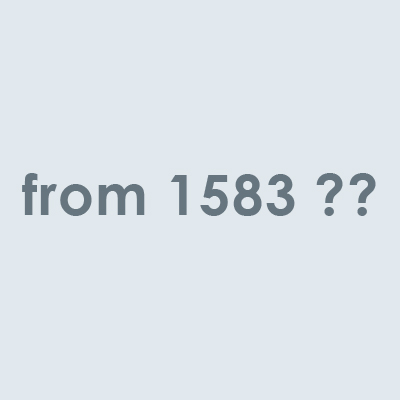
Wednesday,September 2
ツェラーの公式の有効範囲はなぜ1583年からなのか
西暦の年月日から曜日を算出する方法として有名なのが「ツェラーの公式」です。銀行などでも利用されているほど信頼性が高く、なによりも年月日を代入するだけで曜日が算出できるというとても使い勝手の良い公式です。
ですが、「ツェラーの公式」にはひとつ注意事項があります。有効範囲が1583年から3999年となっていることです。
上限の3999年は、まあ計算限界の有効範囲としてあり得そうな数字ですから納得もできそうなものですが、下限となっている1583年は中途半端な数字です。
どうして下限が1583年となっているのでしょう?
これを知るためには、計算では窺い知れない暦の歴史を紐解く必要があります。
そもそも、暦というものが誕生して間もないころ、暦は今のように誰もがその恩恵を享受できるものではありませんでした。暦は、農耕においては種まきや収穫の時期を知るための大事な指標でしたから、西暦(グレゴリオ暦)の100年くらいまでは、その時のローマ皇帝が即位する度にその都度「今日をグレゴリオ暦○年○月○日とする」と好き勝手に決めていました。暦は時の権力者の権力を象徴する物でもあったのです。
しばらくして歴史が移り変わると、西暦(グレゴリオ暦)の決定権は教会へと移行しました。ヨーロッパの教会には必ず鐘つき堂がありますよね。あれは、教会がまわりの人々に時刻を教えるためのものです。時刻や暦は教会が決めていました。相変わらず暦は権力の象徴ではありましたが、教会は恣意的に暦を運用しようとは思わなかったようです。
さらに時代が進むとともに、天文学も進みます。観測装置も進歩して惑星の周期が驚くべき精度で観測できるようになり、1年のほぼ正確な間隔が計算できるようになりました。それは同時に、いままで精度の悪いやり方で進めざるを得なかった暦とのズレも、ほぼ正確に検算できたということです。検算すると、当時使われていた暦と正確な暦とでは10日もズレていたことがわかりました。
当時のローマ・カトリック教会はこれを深刻に受け止め、改暦委員会に暦法改正を委託しました。同委員会は作業の末に完成した新しい暦を、1582年2月24日に発布しました。それは、1582年10月4日(木曜日)の翌日を、1582年10月15日(金曜日)とするという驚くべきものでした。4日の次の日が10日になるなんて、いまではとても考えられませんよね。当時の人々も大混乱したのではないでしょうか。記録があれば見てみたいものです。
結果、1582年10月15日以前の暦は計算とはズレたものを運用していたという歴史上の現実がありました。
これで「ツェラーの公式」の有効範囲の下限が1583年となっている理由がわかりますね。ツェラーの公式に下限以前の年月日を代入しても曜日は出てきますが、実際の歴史上の曜日とは異なるので使えないということになるのです。
1582年10月15日以前の暦はかなりあやふやになります。
遡れば遡るほどに歴史上のグレゴリオ暦と計算上とのそれはズレていきます。
最後にひとつ大命題。西暦0年はイエス・キリストが生まれた年とされていますが、それは計算上の西暦で言うと何年なのか。もうひとつ。キリストが生まれた日は何曜日だったのか。
実はこれ、単純そうに見えてかなりの難問です。
歴史学者でも答えを出すのは難しいでしょう。
≫ NEXT_LOG ジグゾーパズル1000PCS.への挑戦【第5日目】
≪ PREV_LOG ジグゾーパズル1000PCS.への挑戦【第4日目】
スタジオムーンリーフ(2005年1月開設/Since 2005)
代表者:野口 卓洋(Takuhiro Noguchi)
Add:356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘3-1-22-504
Twitter:@StudioMoonLeaf
Facebook:facebook.com/noguchi.takuhiro

©2017 STUDIO MOON LEAF ALL RIGHTS RESERVED.